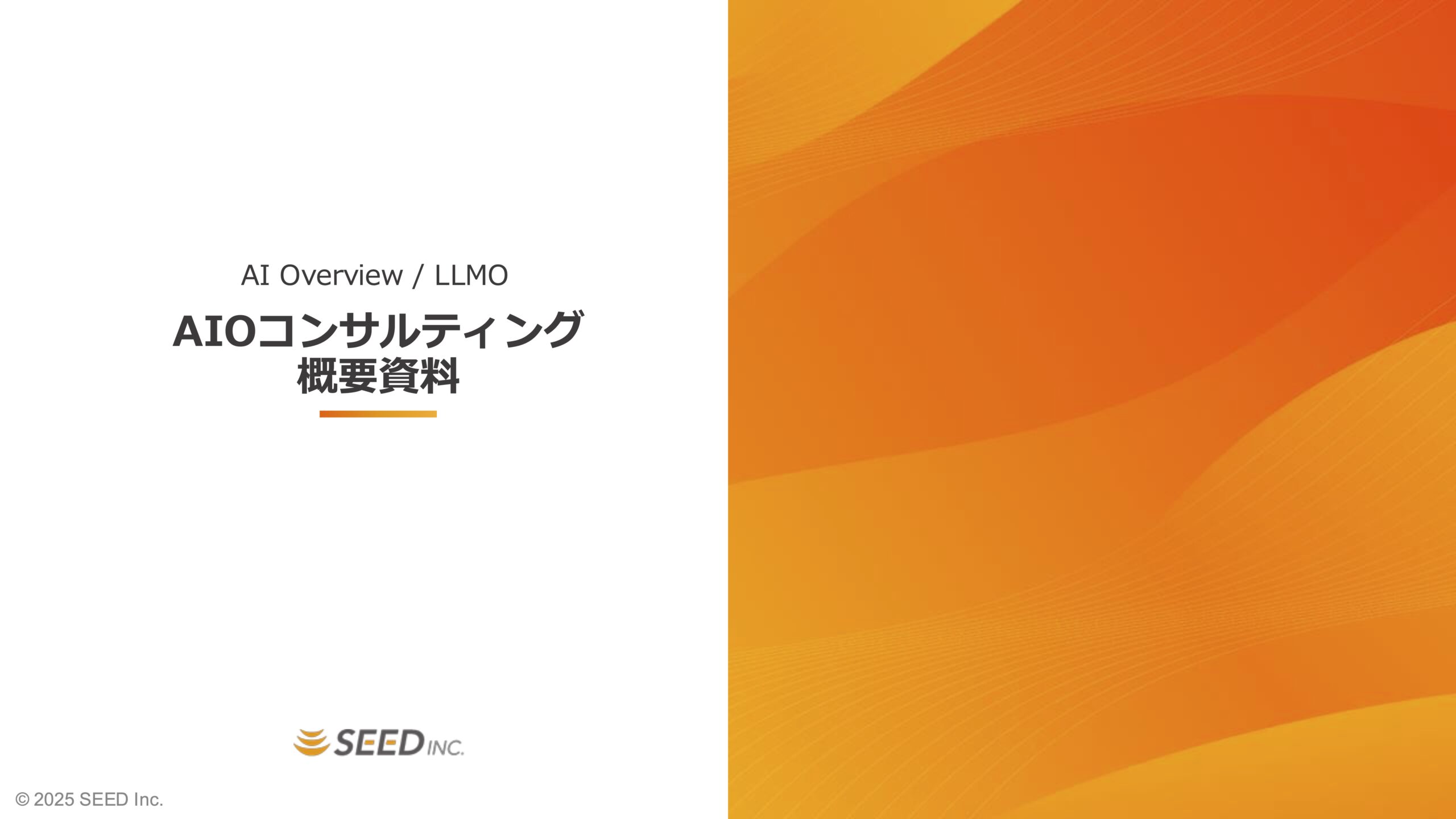AI検索時代において、SEO(検索エンジン最適化)だけでは不十分です。今、「GEO(生成AI・検索エンジン最適化)」対策が注目されています。
AIが情報を収集・統合する仕組みが進化する中、AIにコンテンツを正しく理解させ、信頼できる情報源として認識されることが不可欠です。
本記事では、GEO対策の基本から具体的な施策を優先度別に詳しく解説します。AI検索時代を勝ち抜くためのGEO戦略を身につけましょう。
AIO・LLMO対策の悩みを解決!
1『無料相談会』:最短30分で運用改善ポイントをご案内
2『AIOコンサルティング概要資料』:広告運用&メディア運営で培った圧倒的ノウハウ
3『AIO・LLMO入門ガイド』:AIO・LLMOがゼロからわかる!
4『AIO対策・LLMO対策完全攻略ガイド』:具体的な対策ノウハウを公開
GEOとは?

GEOは、生成AIが検索結果を作成する際に自社の情報を引用してもらうための最適化戦略です。GEOではChatGPTやGeminiのような生成AIが回答文を組み立てる際に、自社サイトの情報が根拠として使われる状態を目指します。
GEOはAI時代のブランド露出にも直結する中核施策です。ユーザーとの接点を生み、将来の検索体験の変化にも柔軟に対応できるのがGEOの強みと言えます。
マーケティング・ビジネスにおけるGEOの重要性
GEOは、マーケティングやビジネスの現場において欠かせない視点になりつつあります。なぜなら、AIが解釈した情報を活用する場面が増え、企業の魅力やサービス内容が、AIにどう伝わるかが、成果に大きく影響するようにシフトしているからです。
従来のSEOは検索順位を上げる発想が中心でしたが、GEOは顧客接点全体を視野に入れ、ブランドの理解や信頼の形成を重視します。商品やサービスをどう見せるか、どのように選ばれるかといった要素が、戦略の核です。
具体的な活用方法や実践のステップについては後ほど詳しく解説していきます。
GEOが重要な理由
GEOが重要とされる最大の理由は、AI検索時代における露出機会の質と量を左右するからです。生成AIはユーザーの質問に対し、膨大な学習データから最適な情報を要約して提示します。
その回答文の中に自社の情報が含まれれば、従来の検索結果以上に強い訴求が可能です。AIに選ばれる存在になれば、検索画面からの流入やブランド認知の向上につながり、さらなる利益の拡大が見込めます。
【ゼロからわかる!AIO・LLMO入門ガイド】はこちら
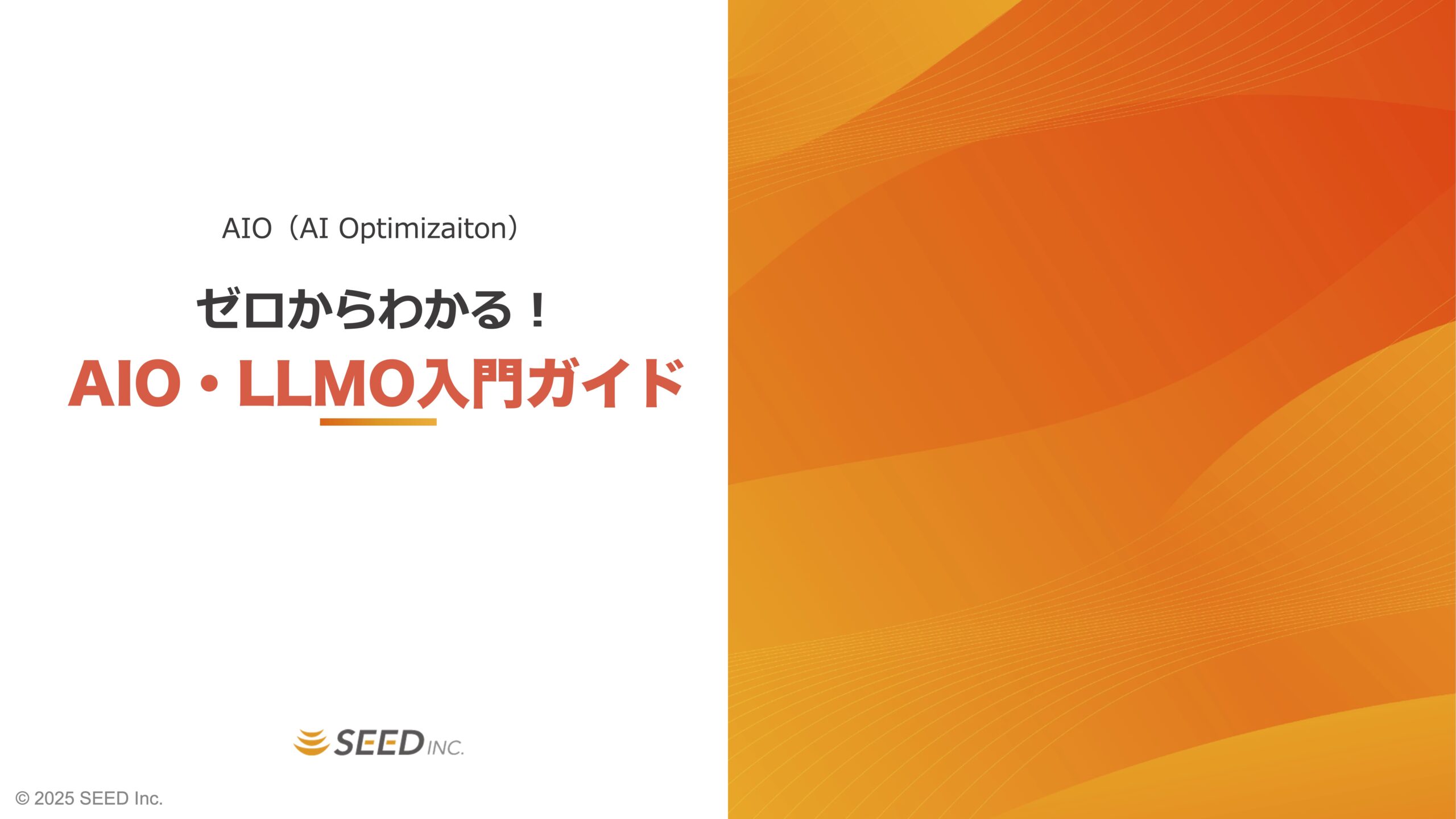
- AIOを「なんとなく知っている人」で終わらせますか?それとも「本質を理解して市場をリードする人」になりますか?いま行動できる人だけが、競合が手を出せていないブルーオーシャンを先取りできます。今すぐダウンロードして、AIOで一歩先を走りましょう!
GEOとAIO・LLMO・SEOとの違い

検索や情報収集の世界は、日々めまぐるしく進化しています。新しい概念や手法が次々に生まれ、名前を耳にしても詳しくはわからないことも多いですよね。
GEO、AIO、LLMO、SEOといった言葉も、その一つかもしれません。ここでは、その違いをわかりやすく紹介し、今後の活用のヒントにつなげていきます。
| 特徴 | GEO | AIO | LLMO | SEO |
| 目標 | 生成検索で露出最大化 | AIに使われる情報設計 | 回答本文で根拠として言及 | 検索順位アップ→クリック獲得 |
| 主戦場 | AIカード/関連枠 | 回答本文 (構造化情報がそのまま採用) |
回答本文 (言及・出典) |
SERP (検索結果画面) |
| 主な施策 | エンティティ整備 商品カード最適 |
FAQ/構造化・短文化 | 一次データ・事例公開 用語統一 |
コンテンツ最適 内部対策 外部対策 EEAT対策 |
| 例 | 「おすすめ」でカード掲載 | FAQがそのまま回答に採用 | 白書・検証が本文で引用 | 記事・LPが上位表示 |
AIOとの違い
AIOは、生成AIや検索AIが理解しやすく、回答や推薦に取り入れやすい形で情報を設計する対策方法です。AIOはAIの言語理解や文脈処理に合わせてコンテンツを作ります。
GEOとの違いは、GEOが生成AI時代の包括的な検索戦略であるのに対し、AIOはその中でAIに好まれる情報設計に特化している点です。SEOやGEOなどと組み合わせて活用することで、検索結果とAI回答の両方で露出を広げられます。
LLMOとの違い
LLMOは、ChatGPTやClaudeのような汎用大規模言語モデルに情報をわかりやすく届ける考え方です。幅広い用途のAIが理解しやすく、対話や文章生成に活用できる形でデータやコンテンツを設計します。
例えば、LLMOでは企業のマニュアルをAIに学習させ、カスタマーサポートを効率化するといった活用ができます。GEOとの違いは、LLMOが幅広い対話型AIに適した設計を重視するのに対し、GEOは検索エンジン的な生成AIを意識した最適化という点です。
両者をうまく使い分けることで、AI時代における露出や信頼獲得の可能性はさらに広がります。
SEOとの違い
SEOは検索エンジンの順位を上げ、リンクをクリックしてもらうことでアクセスを増やす施策です。アルゴリズムを意識したキーワード配置や内部リンク設計、被リンク獲得などが主な手法です。
SEOでは、サービスページやコラム記事を上位表示させることを目指します。目的が「クリックしてもらう」であるのに対して、AIOの目的が「AIの回答に組み込まれる」へと変わる点が大きな違いです。
それぞれをうまく組み合わせると、検索結果とAI回答の両方から集客効果を高められます。

GEO対策を行うべき理由

GEO対策は、これからのオンライン戦略に欠かせない取り組みです。その必要性を示す主な理由は下記の3つです。
- AIによる検索が拡大しているため
- 将来の検索技術にも対応する可能性があるため
- 変化に強いコンテンツ基盤を作れるため
AIによる検索が拡大しているため
AIによる検索は急速に拡大しており、今後も成長が見込まれます。その波に乗るには、早い段階からGEO対策を進めておくことが大切です。
対応が遅れると、検索エンジン経由の流入が減少し、結果的に売上にも影響が出る恐れがあります。
また、自社サービスがAIのレコメンドに含まれなければ、指名買いのチャンスを逃してしまいます。逆に、早期にGEO対策を行いAIに選ばれる情報構造を整えておけば、検索行動が変化しても安定した露出が期待できるのは、大きなメリットです。
ここで言う「AIのレコメンド」は、生成AIや生成検索が回答や関連枠で、特定のブランドや商品、記事を「候補や根拠として」提示・引用することです。今後の市場で優位に立つためには、SEOと並行してGEO対策を進めましょう。
将来の検索技術にも対応する可能性があるため
将来の検索技術は、音声検索やAR検索など多様な形に進化すると考えられます。その中心には生成AIがあり、ユーザーの求める情報を瞬時に整理して提示します。
今からGEO対策をして、AIに正しく評価されるコンテンツを整えておくことが重要です。
例えば、音声アシスタントが近隣店舗を案内する際に、自社情報が優先的に読み上げられれば、来店や購入の機会が広がります。AR検索で街中の看板をスキャンした際に、AIが自社サービスを関連情報として表示すれば、オフラインからの集客にもつながります。
変化のスピードが早い市場で継続的な露出を確保するには、今のうちから未来を見据えた対策が不可欠です。GEOはその土台を築く重要な取り組みと言えます。
変化に強いコンテンツ基盤を作れるため
GEO対策は、将来の環境変化にも耐えられる強固なコンテンツ基盤を作る上で有効です。GEO対策では質の高い情報を中心に設計するため、検索エンジンのアルゴリズムが変わっても影響を受けにくくなります。
結果的に、生成AIの回答やレコメンドにも取り上げられる確率が高まります。このような基盤は新しいマーケティング施策やメディア展開にも流用しやすく、長期的な集客とブランド価値の向上に効果的です。
安定した成果を出し続けたい企業にとって、GEO対策は持続可能な成長戦略の土台と言えます。
【AIO対策・LLMO対策完全攻略ガイド】はこちら
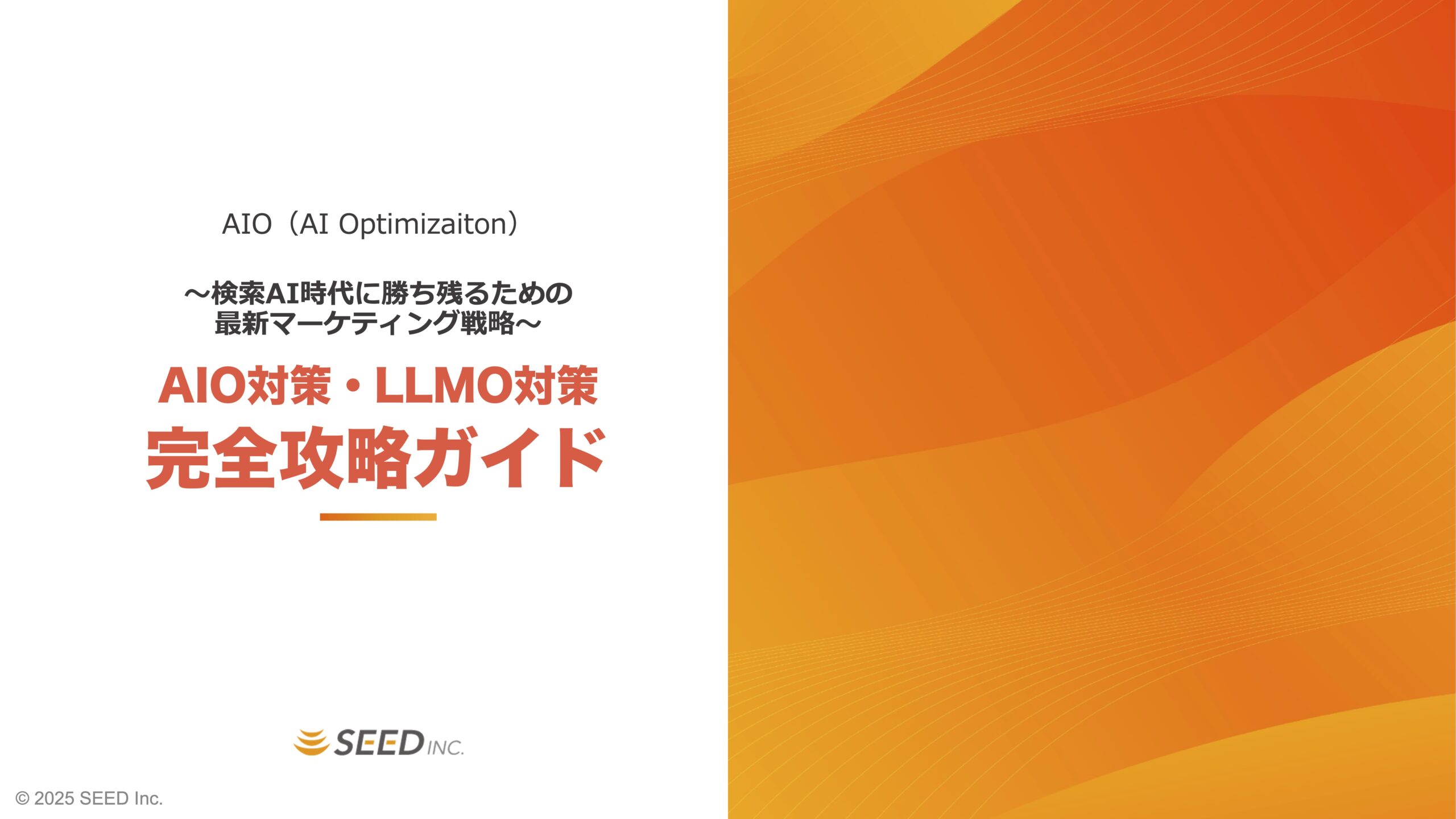
- AIOを「なんとなく知っている人」で終わらせますか?それとも「本質を理解して市場をリードする人」になりますか?いま行動できる人だけが、競合が手を出せていないブルーオーシャンを先取りできます。今すぐダウンロードして、AIOで一歩先を走りましょう!
GEO対策おすすめ14選

ここからは、GEO対策の中でも特に注目すべき対策を優先度に分けて、14個紹介します。
GEO対策は成果を伸ばす強力な武器ですが、方法により効果や取り組みやすさが異なります。
ここでは、3つの優先度別に紹介します。
【優先度★★★】GEO対策7選
先に、優先度の高い7つの施策を確認しましょう。
- 引用されやすい要素を盛り込む(引用・統計)
- 簡潔で直接的な回答を提供する
- EEAT対策を強化する
- 構造化データを活用する
- wikipediaページを取得し管理する
- エンティティ関連ページを最適化する
- 権威ある第三者メディアに露出する
引用されやすい要素を盛り込む(引用・統計)
引用や統計を効果的に盛り込むことは、AIに参照されやすいコンテンツ作りの基本です。権威ある情報源からの引用は、記事の信頼性を一気に高めます。
また、自社が独自に実施したアンケートや調査データを掲載すれば、一次情報としての価値が増し、他では得られない情報源として選ばれる可能性が高まります。統計や数値は文章だけでなく、グラフや表を用いて視覚的に整理することで理解度も向上します。
このように、信頼性と独自性を兼ね備えた情報はAIの引用対象となりやすく、GEO対策の核となる要素です。
簡潔で直接的な回答を提供する
簡潔で直接的な回答を提供することは、AIに選ばれるコンテンツ作りの重要なポイントです。生成AIはユーザーの質問に対して、短く明確な文章を優先して抽出します。
また、専門用語は短い説明を添えることで、一般ユーザーにも理解しやすくなり、離脱率の低下や滞在時間の向上にもつながります。
明確で簡潔な回答は、SEOとGEOの両面で効果を発揮する戦略的な要素です。
EEAT対策を強化する
EEAT対策を強化することは、AIに選ばれるための最も基本的な土台です。EEAT(経験や専門性、権威性、信頼性)が明確に示されたコンテンツは、その評価を大きく高めます。
AIは回答を作成する際、信頼できる情報源を優先して参照します。
また、外部からの引用や被リンクを得ることで、第三者からの信頼も可視化できます。このような積み重ねが、検索結果やAI回答において選ばれるコンテンツにつながります。
構造化データを活用する
構造化データを活用することは、AIにコンテンツを正しく理解させるために有効です。検索エンジンの公式ドキュメントでも、一部の情報整理に役立つことが認められています。
イベント情報であれば、日時や場所、参加方法を明確にマークアップすると、検索結果やAI回答での表示精度を向上させることが可能です。
<リッチリザルト テスト>
https://search.google.com/test/rich-results?hl=ja
<スキーママークアップ検証ツール>
https://validator.schema.org/
また、構造化データはFAQやレシピ、記事の著者情報などにも活用できるため、コンテンツ全体の理解度が高まります。
特にGEO対策では、AIが迅速かつ正確に情報を抽出できる状態を作ることが重要です。構造化データは見た目には影響しませんが、裏側でAI評価を底上げする力があるため、早期の導入がおすすめです。
wikipediaページを取得し管理する
Wikipediaは、多くの大規模言語モデルにとって主要な情報源です。ページが存在すれば、ブランドや人物の認識に大きな影響を与えるため、AIが回答を作成する際に引用や参照の対象となる確率が高まります。
また、ページが作成された後も情報の鮮度と正確性を保つため、定期的な更新と管理が欠かせません。
Wikipediaの存在は、検索結果やAI回答におけるブランド露出を左右する重要な資産です。
エンティティ関連ページを最適化する
エンティティ関連ページを最適化することは、GEO対策の基盤を強化する上で欠かせません。企業ページやAboutページを充実させ、ブランドやサービスに関する情報を網羅的かつ正確に整理しておくことで、AIが理解しやすい状態を作れます。
例えば、沿革、所在地、主要メンバー、提供サービス、受賞歴、メディア掲載実績などを明確に記載すれば、外部情報との突合もスムーズです。公式ページで整然と情報を提示しておけば、信頼性が高まり、AI回答で引用される確率も向上します。
権威ある第三者メディアに露出する
権威ある第三者メディアに露出することは、GEO対策の信頼性を一気に高めます。業界誌や専門誌に記事やインタビューが掲載されれば、外部からの評価としてAIにも認識されやすくなります。
こうした露出は、被リンクやサイテーション(言及)を増やし、コンテンツ全体の権威性を底上げします。
また、第三者が評価した実績は潜在顧客の信頼にも直結し、商談や契約の成立率アップの要因です。プレスリリース配信やイベント登壇などもメディア露出のきっかけになり、継続的な発信で掲載機会を増やせるようになります。
【優先度★★】GEO対策2選
優先度の高い施策を7つ実施したら、次に下記の2つの対策することをおすすめします。
- FAQやQ&A形式のコンテンツを強化する
- エンティティ(一貫した固有情報)を管理する
FAQやQ&A形式のコンテンツを強化する
GEO対策で成果を伸ばすなら、FAQやQ&A形式のコンテンツを強化するのが有効です。検索ユーザーは知りたいことを短く質問する傾向があり、その形に沿った情報はAIにも人にもスムーズに届きます。
特に生成AIは、質問と回答のペアを好んで学習・引用するため、質の高いQ&Aは検索結果やAI回答での露出機会を増やします。
例えば、サービス内容やエリア情報などを明確な質問形式にし、簡潔かつ正確な回答を添える方式は有効です。関連する質問を複数並べることで、AIが情報同士の関係性を把握しやすくなり、網羅性の高いコンテンツとして評価されやすくなります。
また、更新頻度も重要です。最新の状況やニーズに合わせて、質問内容や回答をブラッシュアップしましょう。
エンティティ(一貫した固有情報)を管理する
エンティティ情報の整備は、GEO対策で欠かせない施策です。
社名や住所、電話番号、設立年、代表者名などの基本データは、ネット上のあらゆる媒体で一致している必要があります。公式サイトだけでなく、プレスリリースや業界団体の名簿、求人サイトの会社情報ページなど、で相違がないかチェックしてください。
また、電話番号や住所の一部が古いままだと、ユーザーが正しい情報を得られず、機会損失につながります。
さらに、生成AIや検索エンジンは、一貫した固有情報を企業の信頼性指標として評価するため、データの整合性チェックは重要な作業です。
実務では、まず主要な媒体をリスト化し、最新情報に統一する作業から着手すると効率的です。特にプレスリリース配信時や会社概要更新のタイミングで、関連ページも一斉に見直す体制を作ると、長期的に管理が楽になります。
【優先度★】GEO対策5選
ここまでのGEO対策を9つ実施して、余力がある場合に下記を検討しましょう。
- LLMS.txtを活用する
- 物的コンテンツのプリレンダリング・SSR化を実施する
- レビューサイト・ 評価サイトに対応する
- テーマ連動型PRを展開する
- SNSを強化する
LLMS.txtを活用する
LLMS.txtは、生成AIや大規模言語モデルに自社サイトの情報を正しく理解させるためのものです。検索エンジン対策と同じように、AIが参照するデータ源を整えることで、質問応答や記事生成での引用機会を増やせます。
例えば、公式サイトの会社概要や事業内容をLLMS.txtで構造化しておくと、AIが企業名やサービス内容を間違えずに認識しやすくなります。LLMS.txtは単なるファイルではなく、AI時代のブランディング基盤です。
SEOと並行してGEO(生成AI最適化)の視点から、今すぐ導入と情報整備を始めるべきです。
物的コンテンツのプリレンダリング・SSR化を実施する
検索精度を高めたいなら、物的コンテンツのプリレンダリングやSSR化が有効です。
多くのLLMは、現時点でHTMLのみを正確に解析できる仕様を持っています。
もしコンテンツがJavaScript依存の動的生成になっていると、AIが本文を取得できないケースが増え、評価や引用の機会を逃します。
そこで、事前にHTML本文を静的に出力しておく仕組みを導入することで、確実にAIが全テキストを認識できる環境を整えられます。
例えばECサイトの商品ページや企業のサービス紹介ページをSSR化すれば、在庫情報や仕様などの詳細がAI検索にも正しく反映されやすくなります。
検索エンジンだけでなく生成AIからの参照数も増やせるため、マーケティング施策全体の底上げにもつながります。
レビューサイト・ 評価サイトに対応する
AIは製品やサービスを比較するとき、Amazonのレビューや専門サイトの評価を拾い、要約して回答することがあります。検索ユーザーが「おすすめの〇〇」と尋ねた場合、AIはレビューの星の数や具体的な感想を参照し、上位に表示されるブランドを選ぶ仕様です。
もし古い情報や不当な低評価が残っていれば、AIの回答精度だけでなく、ブランドイメージ全体にも影響が出ます。そのため、マーケティング部門では、主要なレビューサイトを定期的にチェックし、必要に応じて最新情報の反映や改善策を講じることが重要です。
具体的には、新製品の発売時に専門サイトへ試用機を提供して記事化を促したり、既存顧客へのフォローアップでポジティブなレビューを増やしたりする施策が効果的です。
レビュー情報を整備しておけば、AIによる比較やレコメンドでも有利に働き、結果的にGEO領域での集客力向上につながります。
テーマ連動型PRを展開する
ブランド認知を高めたいなら、テーマ連動型PRの活用が効果的です。単なる製品情報の発信ではなく、ブランドと特定のテーマを一貫して結び付けることで、検索やAI要約の中でも印象を残しやすくなります。
AIやLLMOはニュースや記事を要約するときに、テーマ部分も拾う傾向があるため、露出のたびにブランドの世界観が強化されます。
また、SNS運用やイベント出展でも同じテーマを盛り込み、一貫したメッセージを発信します。担当者は、広報や広告チームと連携してテーマ設定を行い、全チャネルで統一感を持たせることが重要です。
テーマとブランドをセットで、覚えてもらえる仕組みを作りましょう。
SNSを強化する
GEO対策を加速させたいなら、まずSNSの発信力を底上げしましょう。単に情報を流すだけでなく、業界や特定トピックで信頼される発信者として認知されることが重要です。
例えば、BtoB企業なら、最新の業界動向や市場データを定期的に解説し、自社の視点や提案を交えて投稿します。BtoCブランドであれば、商品の使い方や開発ストーリーをビジュアルと共に発信し、ファンとの双方向コミュニケーションを促します。
ポジティブな言及を増やすには、インフルエンサーや既存顧客とのコラボも有効です。フォロワーの投稿をリポストしたり、参加型キャンペーンを展開したりすることで、自然な口コミが広がります。
SNSの継続的な発信はGEO表示にも好影響を与えるので、経営者やマーケティング担当者は戦略的にSNSを育てる必要があります。社内にリソースがない場合は、外部に依頼することも有効です。
GEO対策なら株式会社シードへ

シードは、AIO・GMOの初期段階から注目し続けてきたスペシャリスト集団です。20年以上にわたるWebマーケティングの経験を持つ広告代理店として、多くの企業の集客や売上向上をサポートしてきました。
自社メディア「デジマ部」で培った豊富な実践知識をAIO領域・GMO領域にも展開し、検索AI時代における効果的な施策を提案します。AI時代にはマルチチャネル戦略が不可欠であり、シードはWeb広告戦略における設計から実装、効果検証まで一貫した支援が可能です。
先を見据えたAIO対策・GMO対策を求める企業にとって、信頼できるパートナーです。
GEOに関するよくある質問

GEO対策をしないとどうなりますか?
GEO対策を怠ると、AI検索で自社コンテンツが回答に引用される機会が減少する恐れがあります。その結果、検索経由の新規訪問者数が大きく減り、見込み客との接点が失われます。
また、AIがレコメンドする候補から外れると、指名買いを狙える瞬間を逃してしまう点も注意が必要です。例えば、地域名と業種で検索された際に競合が推薦され、自社は表示されない状況となります。
特に新規顧客獲得の要となるローカル検索では、数ヶ月で顧客数が数十%減る事例もあります。継続的に集客と売上を維持するなら、今すぐGEO対策を着手することが不可欠です。
GEO対策を実施すると、SEOで培った資産が無駄になりませんか?
SEOで積み上げた資産は、GEO対策でもしっかり活かせます。高品質なコンテンツや専門性・権威性・信頼性を示すEEAT、さらに検索エンジンに情報を正確に伝える構造化データは、GEOでも評価されやすい要素です。
例えば、地域名を含めた記事がすでにSEOで上位表示している場合、その情報をAI検索やローカル検索での引用につなげることが可能です。
また、店舗情報やレビューを構造化データで整備すれば、地図検索やAIレコメンドにも表示されやすくなります。
SEOとGEOは対立するものではなく、相互に補完しながら集客力を高める関係です。既存の資産を最大限に活かして、新しい流入チャネルを広げていきましょう。
EEAT(経験、専門性、権威性、信頼性)はGEOでどう活かせますか?
EEATは、GEO対策においても強力な武器です。AIは正確で信頼性の高い情報を優先的に参照する傾向があり、経験や専門性、権威性を示したコンテンツはAIの回答に採用されやすくなります。
例えば、専門家の監修コメントを盛り込んだ記事や、政府機関・業界団体など信頼度の高いデータを引用した記事は評価が高まりやすいです。著者プロフィールで経歴や実績を明示すると、情報の信ぴょう性が一段と高まります。
SEOで培ったEEATの要素をGEO向けにも展開すれば、AI検索やローカル検索でも露出が拡大します。
GEO対策はいつから始めるべきですか?
GEO対策は思い立った瞬間から着手するのが理想です。AI検索はまだ進化の途中ですが、ユーザーの利用は確実に増えており、早く動いた企業ほど優位に立てます。
準備が整った頃には競合も動き始めるため、先行者のポジションを取れるかどうかが大きな分かれ道です。早期にGEO対策を始めれば、AI検索の精度が高まった段階で自社情報が上位表示される確率も高まり、集客の波に乗りやすくなります。
GEO対策は長期的な視点で取り組むべきですか?
GEO対策は短期的な成果だけを狙うのではなく、長期的な視点で進めることが欠かせません。AI検索は日々精度を上げており、音声検索やAR検索といった新しい検索形態も次々と広がっています。
例えば、地域別に細分化した記事を定期更新したり、実店舗の写真や動画を充実させたりする取り組みは、効果的です。一度作ったコンテンツも放置せず、最新情報やユーザーニーズに合わせて改善を重ねることで評価が積み上がります。
時間をかけて信頼を構築すれば、変化の激しい検索環境でも安定的に集客できる強い土台を築けます。
まとめ|GEOとは生成AI時代における必須の対策

GEO対策は、生成AI時代の情報発信において欠かせない取り組みです。単なる検索対策ではなく、未来の検索環境に適応できる強いコンテンツ基盤をつくることがポイントです。
AI検索や音声検索、ARなど多様な検索手段が広がる中で、質の高い情報を継続的に発信すれば、長期的に信頼を積み重ねられます。今から一歩踏み出し、継続的に改善を重ねることで、変化の激しい時代でも安定した成果を得られるようになります。
 無料相談
無料相談